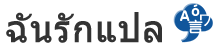- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
現代タイ語のあゆみ 4何故「音価」の同じものが違う文字になったのか、そ
現代タイ語のあゆみ 4
何故「音価」の同じものが違う文字になったのか、その理由は
①タイ語では古くは声調符号と声調型とは対応関係を持っていた。
②音節初頭子音の変化に伴なって、声調型を変化したために両者間
にずれが生じた。
③このため音韻変化により「同音異字」が生まれた。
④パーリ・サンスクリット語でも、発音よりも原形が重視され「文
字」と「発音」の乖離が激しく(借用語に多い)
これ等の条件を満たすために工夫されたものである。実はタイ人でもどの字を使うのか迷うことがあると言う。
現代のタイ語が「国語学」として確立するのは1918年「タイ語の基礎・ラック・パーサー・タイ」と言う本格的「文法書」が出されてからである。未だ100年も経ってない。
「新方式の採用」
それまでのタイ語の教育は「母音」「子音」「声調」と言った「音韻学的」説明から始めるものであった。今から60年程前からは、「読み書き」の導入部分で「日常の単語」の身の回りの易しい意味を持つ言葉(単語)や文章を教え徐々に「音韻学」ないし「音声学」的説明を加えていくと言う方法への変化である。
「コー・カイ」から始めるのではなく、「ก― า กา =カラス」「ห ―ม― า หมา=犬」と言った「単語」を最初から教えて行く方法の採用である。1960年頃には現在のような「国語教科書」が完成した。このように「あゆみ」を見て来ると、可なりの期間が掛かって「現代タイ語」が出来上がったのである。 続く
何故「音価」の同じものが違う文字になったのか、その理由は
①タイ語では古くは声調符号と声調型とは対応関係を持っていた。
②音節初頭子音の変化に伴なって、声調型を変化したために両者間
にずれが生じた。
③このため音韻変化により「同音異字」が生まれた。
④パーリ・サンスクリット語でも、発音よりも原形が重視され「文
字」と「発音」の乖離が激しく(借用語に多い)
これ等の条件を満たすために工夫されたものである。実はタイ人でもどの字を使うのか迷うことがあると言う。
現代のタイ語が「国語学」として確立するのは1918年「タイ語の基礎・ラック・パーサー・タイ」と言う本格的「文法書」が出されてからである。未だ100年も経ってない。
「新方式の採用」
それまでのタイ語の教育は「母音」「子音」「声調」と言った「音韻学的」説明から始めるものであった。今から60年程前からは、「読み書き」の導入部分で「日常の単語」の身の回りの易しい意味を持つ言葉(単語)や文章を教え徐々に「音韻学」ないし「音声学」的説明を加えていくと言う方法への変化である。
「コー・カイ」から始めるのではなく、「ก― า กา =カラス」「ห ―ม― า หมา=犬」と言った「単語」を最初から教えて行く方法の採用である。1960年頃には現在のような「国語教科書」が完成した。このように「あゆみ」を見て来ると、可なりの期間が掛かって「現代タイ語」が出来上がったのである。 続く
0/5000
ประวัติศาสตร์ทางเลือก 4 ปัจจุบันทำไม "ค่า" อักขระเดียวกันจะแตกต่างกัน สิ่งที่เป็นเหตุผล(1)จากวันที่ในประเทศไทย ได้โต้ตอบกับเครื่องหมายกำหนดเสียงและโทนสี(2) พยางค์ในฟอร์มต้นของพยัญชนะเปลี่ยนชนิดเสียงระหว่างสอง ความเหลื่อมล้ำ(3 เกิดการเปลี่ยนแปลง)โครงสร้างประโยคเนื่องจาก "homophones(4) ในภาษาบาลีและสันสกฤตเน้นการออกเสียงเดิมมากกว่า "ประโยค - " และการออกเสียงของการ (มักจะยืมคำ)ควรออกแบบให้ตอบสนองความต้องการนี้ ผมบอกว่า รับใช้สูญหาย หรือแม้แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยซึ่งตัวละคร1918 มูลนิธิแห่งประเทศไทย และไทยแบ่งชั้นพูดไทยสร้างเป็น "ภาษาศาสตร์" แท้ "ไวยากรณ์" จาก ยังน้อยกว่า 100 ปี"การยอมรับของวิธีการใหม่ภาษาไทยจนมันคือเวลาเริ่มต้นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ "สระ" และ "พยัญชนะ" เสียง "และกล่าวว่า บางสิ่งบางอย่าง ค่อย ๆ ตั้งแต่วันนี้จาก 60 ปีความรู้สึกง่าย "ทุกคำ" ในการ "อ่าน/เขียน" การนำคำ (คำ) และไวยากรณ์สอน "กับภาษา" หรือ "เสียง" ในการเปลี่ยนวิธีหนึ่งของการเพิ่มคำอธิบายแทนที่เริ่มต้นจากเกาะไข่ "กกา =อีกา]] " ' ห -ม-]] หมา =สุนัข "และควรวิธีการสอนจากคำแรกที่กล่าวว่า ปัจจุบันเช่นในปี 1960 ตำราเสร็จสมบูรณ์ มาดูทางนี้ "ประวัติศาสตร์" และแขวนรอบระยะเวลาจะอนุญาต และปัจจุบันภาษาอื่นอยู่ใน ตามด้วย
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาสมัยใหม่ไทย อายูมิ" ทำไม ค่าเดียวกันของอักขระที่แตกต่างกัน เหตุผลฉันพูดไทยในสมัยโบราณที่ความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และเสียงประเภทการเปลี่ยนแปลงของพยางค์พยัญชนะที่จุดเริ่มต้นของทางรถไฟระหว่างสองเพื่อเปลี่ยนประเภทโทนการเกิดขึ้นดังนั้น ไม่ว่า " การเปลี่ยนแปลงทางโฮโมโฟนิค 'แม้ในบาลี และสันสกฤตออกเสียงประโยค ว่า " มีความสําคัญกับต้นฉบับ" และ " ความแปลกแยก " ของฮาร์ดดิสก์ ( ภาษา )ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองเงื่อนไขเหล่านี้ ที่บอกว่าไทยตัวจริงภาษาศึกษาไทยสมัยใหม่ และสร้างพื้นฐาน・ラック・パーサー・タイ 1918 " และ " ไทยแท้ " คำ " ในไวยากรณ์ ไม่ถึง 100 ปีการยอมรับของ " ระบบใหม่ "มันคือภาษา การศึกษาไทย " " " " " " " พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ กล่าวว่า " ไม่มี " ก็สามารถอธิบายได้จากการเริ่มต้น จากนี้ไป เมื่อ 60 ปีก่อน คำว่า " จาก " และ " แนะนำส่วนหนึ่งของทุกวันคําธรรมดา " ความหมายของคำและประโยค หนึ่งคือการบอกวิธีเพิ่มรายละเอียด " สัทศาสตร์และสัทวิทยา " ไม่สอน " ค่อยๆ "เริ่มจาก " ชิ " แทน " อีกา " . . . ากา = " - - หแองาหมา = หมา " เขากล่าว " จากคำแรกไปสอน เป็นลูกบุญธรรม เสร็จสมบูรณ์ " หนังสือเรียน " ในประมาณปี 1960 เช่นตอนนี้ มา และเห็นเป็น " ประวัติศาสตร์ " และแขวนในภาษาสมัยใหม่ของไทย " เสร็จ " ตาม
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- การสื่อสารกับผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างส
- จู่จี้
- ทอดกระเทียมพริกไทย ปลากะพงแดง
- Piezoelectric oxides Pb1−xLax(ZryTi1−y)1
- . And I want to work at Bangkok Bank Pub
- GSH and Cys were purchased from Sigma
- มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
- ในจังหวัดนราธิวาส
- มันแค่เป็นรอยร้าว หัวมุมเล็กน้อย
- AUTONOMOUS BEHAVING SYSTEMS
- Taxonomy
- unanimously
- เกาะพีพี
- reading comprehension
- Heat water to boiling Bring to boil the
- นี่แซนวิส
- วันนี้ฉันตื่นสายมากๆเพราะว่าเป็นวันหยุด
- Nowadays, social media's role in society
- ฉันทำทุกอย่างเพื่อเราสองคน
- Finger lickin good suggests that
- No-Wear Products.
- ประนีประนอม
- Crossbreeding of Pangasianodon hypophtha
- ใช้บริเวณรักแร้